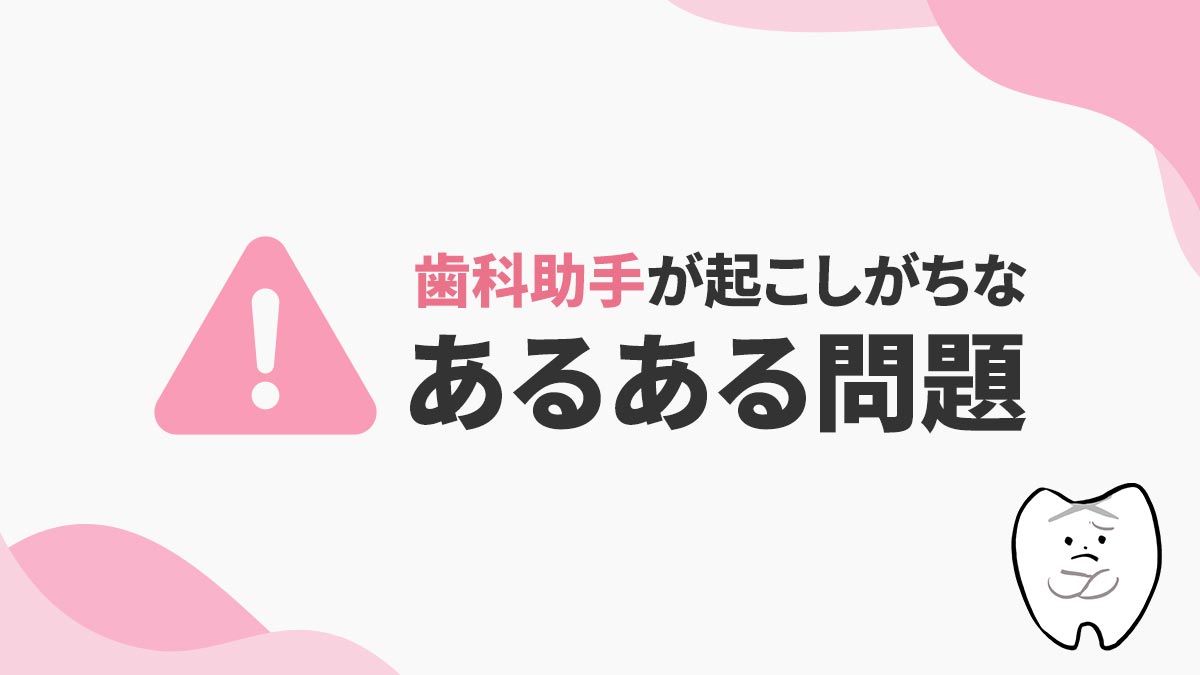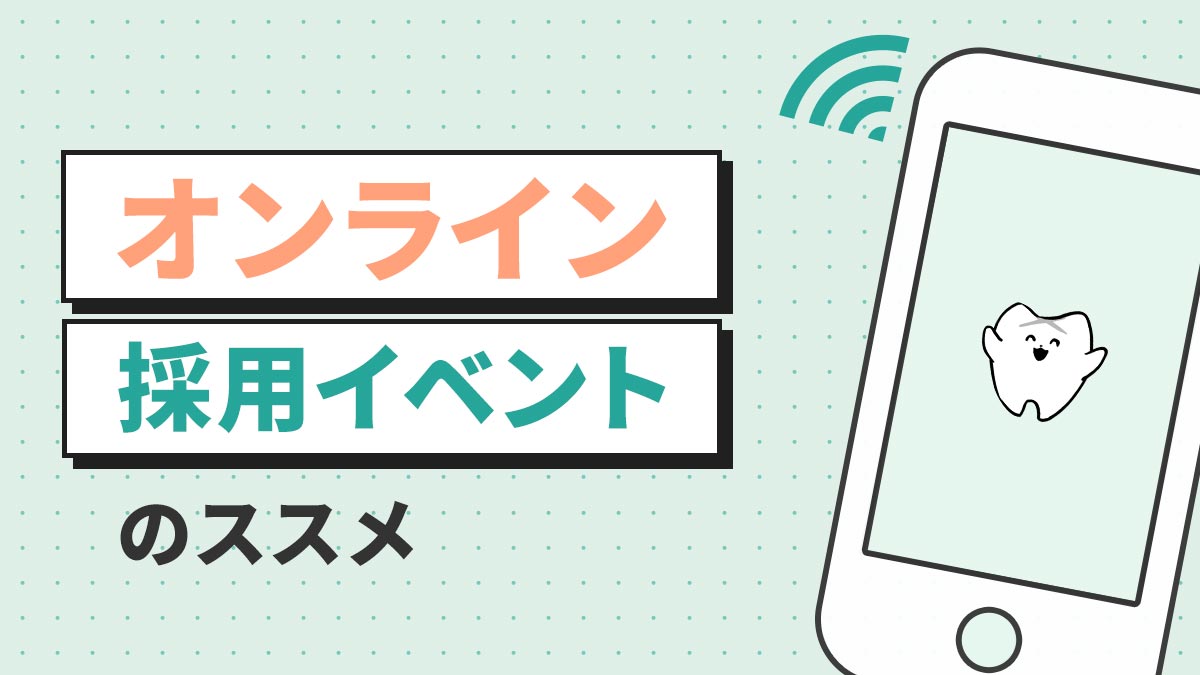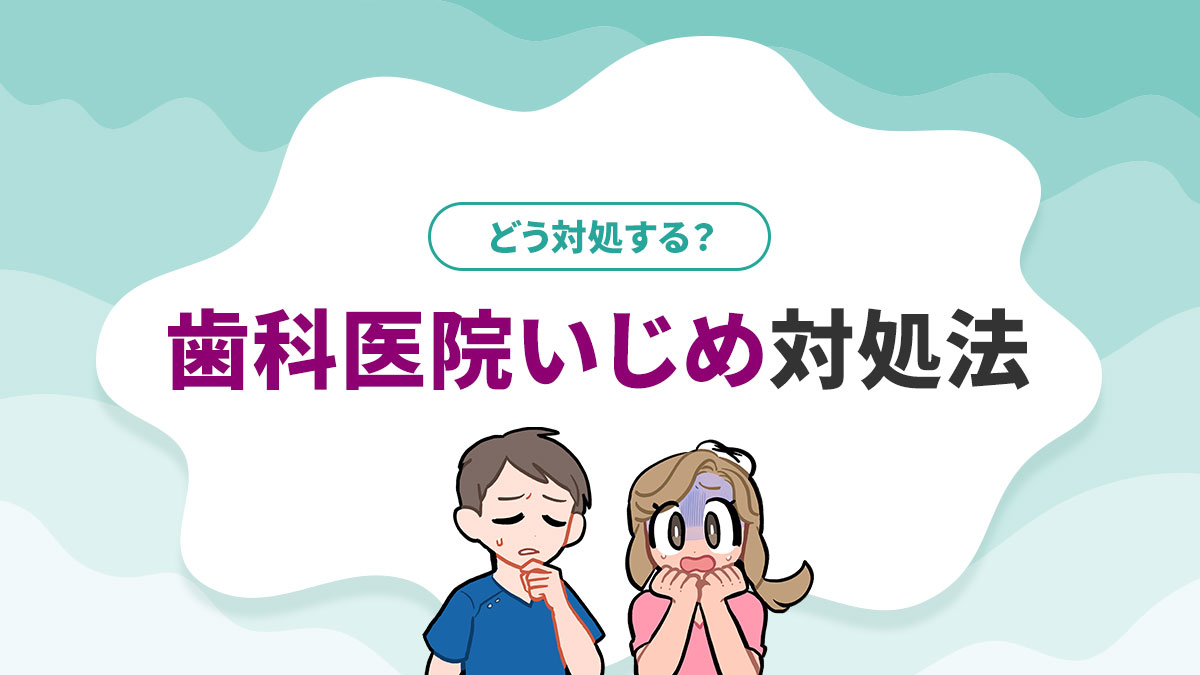歯科助手の仕事と役割は、多岐にわたります。
診療室内での患者さんのケアからユニット、医療器具の管理まで多岐にわたります。歯科助手の働きによって、歯科医療の質と効率が向上し、患者の安心感と満足度が高まります。そして、歯科医師や歯科衛生士をはじめとする歯科医院のスタッフ全体が円滑に連携するための重要なポジションです。
歯科医院を運営する中で、助けられている先生方も多いでしょう!
歯科助手あるあるを知って上手に付き合うニャ!
歯科助手と歯科医師の関係性と協力の重要性
円滑な診療と患者さんのケアには、歯科助手と歯科医師の関係性は非常に重要です。
歯科助手と歯科医師は、相互に信頼し合い、連携を図ることで、より良い医療サービスを提供することができます。
しかし、歯科助手と共に仕事をしていると、コミュニケーション不足や時間管理の問題、個人差によるスキルの違い、ストレスによる仕事の質の低下など、様々な課題に直面するのも事実です。
こうした問題は、歯科助手だけでなく、歯科医院全体のパフォーマンスにも影響を及ぼします。なるべく回避したいポイントです。
そこで今回は、「歯科助手あるある」として、歯科助手が陥りやすいミスや問題を紹介します。さらに、ポジティブな部分や、問題を回避するポイントなども解説しています。
歯科助手との対応で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
歯科助手が起こしやすい「あるある」な問題7選

歯科医院を運営するにあたって、歯科助手が起こしやすい「あるある」な問題には、パターンがあります。特に以下の7つは、良く遭遇する問題です。
- 患者情報の取り扱いミス
- 衛生管理を疎かにする
- コミュニケーション不足
- 時間管理が上手くできない
- ストレスによる仕事の質の低下
- 継続的なスキルアップの意欲が低下
- チームワークが不足して連携が取れない
患者情報の取り扱いミス
患者情報の取り扱いミスは、起こりやすい問題の1つです。歯科医院には、毎日多くの患者が来院します。大量の情報に触れる中で注意力が散漫になった結果、起こってしまうのです。
良く見られるのは、カルテの誤記入や患者情報の取り違えです。患者の信頼を損ねる可能性があるため、注意しなければなりません。
衛生管理を疎かにする
衛生管理が疎かになることもあります。理由は、忙しさ。目の前の仕事を優先するあまり、衛生管理を後回しにしてしまうのです。
特に、器具の消毒や歯科医院の清掃がされていないと、患者への感染リスクが高まります。衛生管理の徹底は、安全な治療環境を提供する上で欠かせません。
コミュニケーション不足
歯科助手とスタッフとのコミュニケーション不足は、業務の効率を低下させます。情報の伝達漏れによって、患者対応に混乱が生じるなんてことも。
コミュニケーション不足も、原因は忙しさにあります。忙しくて余裕がなくなってしまう場合は注意しましょう。
円滑なコミュニケーションは、スムーズな歯科医院運営の基盤です。
時間管理が上手くできない
時間管理に苦手意識を持つ歯科助手の場合、時間管理で失敗するケースがあります。特に、予約の取りこぼしや治療時間の見積もりで、ミスが起こりやすいでしょう。
時間管理が上手くいかないと、患者の待ち時間増加に繋がり、不満の原因になります。患者満足度を高める意味でも、時間管理能力は重要な能力です。
ストレスによる仕事の質の低下
高いストレス環境は、歯科助手の仕事の質を低下させます。疲労や焦りからミスが増えたり、患者への対応が冷たくなったり、といった問題が起こります。
ストレス管理は、職場の雰囲気を良くし、仕事の質を保つために重要です。ストレスをためにくい環境作りが求められます。
継続的なスキルアップの意欲が低下
歯科助手が日々のルーティンワークに追われ、新しい知識や技術の習得に対する意欲が低下してしまう点にも、注意が必要です。治療技術の進歩や、社会保険制度に対応できなくなるリスクを孕んでいます。
知識や技術には、定期的なアップデートが必要です。継続的な学習意欲の醸成は、歯科医院のサービス向上に繋がります。
チームワークが不足して連携が取れない
歯科医師や歯科衛生士と一緒になり、チームとしての連携が取れないと、業務の効率が大きく低下します。歯科助手間での情報共有が不足すると、患者対応に支障をきたすことも。
複数人で働く以上、効果的なチームワークは、歯科医院運営の効率化に欠かせません。円滑なコミュニケーションが取れる関係作りが必要です。
歯科助手を雇っていると直面する嬉しい「あるある」も

歯科助手を雇っていると、嬉しい「あるある」にも直面します。特に以下の2つは、ポジティブなケースです。
- 歯科衛生士より仕事ができる
- 歯科助手で雇ったのに優秀すぎてマネジメントを任せた
歯科衛生士より仕事ができる
歯科助手が、予想以上に能力を発揮することは珍しくありません。特に、高い適応能力と学習意欲を持っていた場合です。
良くあるものが、患者対応や診療補助のスキルが、歯科衛生士を上回るケース。このような歯科助手は、医院の運営において重要な柱となってくれます。
嬉しい「あるある」の1つです。
歯科助手で雇ったのに優秀すぎてマネジメントを任せた
歯科助手が、マネジメント能力を発揮するケースもしばしばあります。日々の業務を通じて培ったリーダーシップ能力と思考力によるものです。
例えば、歯科助手が院内のスケジュール管理やスタッフの指導を行い、歯科医院の運営をスムーズにする、といったケースになります。
このような歯科助手は、歯科医院にとって貴重な人材です。中には副院長になる歯科助手もいます。適性に合わせた育成や配置をした結果、才能が花開いたといえるでしょう。
歯科助手の「あるある」な問題を回避できる育成のポイント7選

歯科助手のネガティブな「あるある」は、できれば回避したいものです。そんな場合は、以下の7つのポイントを意識してみてください。
- 定期的な研修や教育の機会を作る
- 業務マニュアルを作っておく
- コミュニケーションしやすい環境を作る
- 定期的にフィードバックをする
- メンターの制度を導入する
- ストレスを解消できる仕組み作りをする
- キャリアアップの機会をわかりやすくする
定期的な研修や教育の機会を作る
効果的な研修と教育は、歯科助手のミスを減らす鍵です。継続的な学習は、知識とスキルの向上に直結し、日々の業務における自信と能力を高められます。
例えば、最新の衛生管理技術や患者対応の研修に定期的に参加すれば、業務の質を向上させることが可能です。
歯科医院全体のスキルアップにも期待できます。
業務マニュアルを作っておく
業務マニュアルの整備は、歯科助手の仕事の質を一定に保つために不可欠です。明確な指示と手順があることで、業務中の迷いや不安を減らし、効率的な仕事の流れを確立できます。「見て覚えろ」が通じていたのは、昔だけです。
歯科医院では、マニュアルがないところも多くあります。あっても不完全で、個人の業務に差が出ている医院も多いのではないでしょうか?一方で業務量は多く、受付対応から治療のアシスタント、在庫管理にレセプト作成など、多岐に渡ります。しかも、相応の知識や経験が必要です。せっかく新人を雇っても、慣れる頃には退職され、また1から教え直しというケースも多々あります。
マニュアル化すると、新人の歯科助手でも、迅速かつ正確に業務を遂行できるようになるため、意識したいポイントです。
また、最近は、実際の業務を動画にして、わかりやすいマニュアルを作るサービスもあります。動画なることで、マニュアルの書き起こしにかかる時間や、微妙なニュアンスの表現による伝達不足も解消できます。活用してみましょう。
参考:「動画マニュアル&教育ツール soeasy buddy for dental」https://pr.soeasybuddy.com/dental/ (外部サイト)
ただし、マニュアルは定期的にメンテナンスしなければいけません。歯科医院の経営方針や制度などの変更があれば、その都度修正し、更新していきましょう。
コミュニケーションしやすい環境を作る
コミュニケーションがしやすい環境は、チームワークと業務効率の向上に直結します。気軽に話せる関係性になると、スタッフ間の誤解を減らし、よりスムーズに業務を遂行できるでしょう。
オススメは、定期的なミーティングや意見交換の場を設けることです。チーム内の信頼関係が深まり、協力しやすい職場環境が生まれます。
定期的にフィードバックをする
定期的なフィードバックは、歯科助手の成長と、業務の質の向上に欠かせません。継続的な評価と建設的な意見を通じて、自分の弱点を認識し、改善の機会を得られます。
実施しやすいのは、個別ミーティングです。定期的に実施することで、歯科助手自身の目標設定と達成度を把握しやすくなります。
メンターの制度を導入する
メンター制度は、新人の歯科助手の早期成長に繋がります。経験豊富な先輩がガイドとなることで、日々の業務に対する理解を深められ、すぐに高いパフォーマンスを発揮できるようになります。多くの企業がメンター制度を導入しているのも、そのためです。OJT(On the Job Training)とも呼ばれています。
メンターとの実践トレーニングを通じて、新人は仕事のコツや対人スキルを効率良く学べます。対応に困った場合は、メンターや他スタッフ、院長がフォローできるようにするのも大切です。
その際、気軽に質問できる雰囲気を作り、間違いやミスに対しても丁寧に指導するよう心がけてください。厳しくすると萎縮して、ミスを隠してしまう可能性があるためです。本人や歯科医院、患者さんのためにもなりません。
また、メンターには適性がある点には注意する必要があります。まずは、メンターに相応しい人材かどうかを見極めるようにしましょう。
ストレスを解消できる仕組み作りをする
ストレス管理は、歯科助手の仕事の質を維持する上で重要です。職場内で、ストレスを解消するためのプログラムや仕組みを作るようにしましょう。精神的にも健康を保ち、仕事のモチベーションを維持できます。
取り組みやすいのは、リラクゼーションスペースの設置や定期的なチームビルディングです。
歯科助手でないと気が付かない部分でストレスを感じている可能性もあるため、個別ミーティングなどでヒアリングすると良いでしょう。
キャリアアップの機会をわかりやすくする
明確なキャリアパスの提示は、歯科助手のモチベーションを高めるために重要です。どのように頑張ればキャリアアップできるのかを、わかりやすく示しましょう。例えば、TC(トリートメントコーディネーター)の資格支援や、歯科衛生士へキャリアチェンジする方法などです。その際、資格やキャリアに対してインセンティブを設けると、モチベーションの向上にも繋がります。
キャリアアップがわかりにくいと、モチベーションも上がりません。目標に向かって頑張れば正当に評価されると、明確にしましょう。
優秀な歯科助手へ育成するのは歯科医院にとって大きなメリット

優秀な歯科助手は、歯科医院にとって欠かせない人材です。どう育成すればいいのかわからないという方は、以下の3つのポイントを意識してみてください。
- 希望があればキャリア支援をする
- 歯科助手のスキルアップは歯科医院の成長に繋がる
- 歯科助手の「あるある」に対処するには適切な配置も大切
希望があればキャリア支援をする
歯科助手が研修などキャリアアップをしようとした際は、キャリア支援をしましょう。自身のキャリアパスを描ける環境かどうかは、非常に重要です。歯科助手のモチベーションを高め、長期的な職場定着に繋がります。
例えば歯科衛生士学校への進学を希望している歯科助手がいた場合、奨学金制度を設けておくとキャリア希望をしやすくなるでしょう。より高いモチベーションで、歯科医院を支えてくれる存在になってくれます。
奨学金制度の助成金なども活用できる場合があるので顧問社労士さんに相談してみるのも手ですよ!
歯科助手のスキルアップは歯科医院の成長に繋がる
歯科助手のスキルアップは、歯科医院全体のサービス向上に直結します。スキルアップにより、さらに高度な治療支援や患者対応が可能になるためです。
「この人がいるから」「丁寧な治療を受けられるから」など、歯科医院事態の魅力で患者さんを惹きつけられます。
マネジメントスキルや最新の歯科技術に関する知識など、歯科医院の成長に繋がるスキルアップは、どんどん歓迎していきましょう。
歯科助手の「あるある」に対処するには適切な配置も大切

歯科助手の適切な配置は、業務の効率化とスタッフの満足度を向上させる効果に期待できます。能力と適性に応じた業務を割り当てるようにしましょう。
例えば、受付業務が得意なら受付に、衛生管理に熟練しているなら衛生を主に扱う業務に配置するといった形です。前職で事務職や接客業の経験があれば、即戦力としても期待できます。採用時の面接や日々の業務を通じて、適性を見極めるよう意識してください。
そうすることで、歯科医院の運営がスムーズになり、患者サービスの質が向上します。適材適所が大切です。
歯科助手を適切に配置するために意識したいポイント7選

歯科助手を適切に配置するためには、意識したいポイントがあります。特に以下の7つは重要です。
- 客観的に評価できるシステムを作る
- スキルと経験を活かせる業務に配置する
- 業務の需要とピークタイムを分析する
- 柔軟なシフト計画を立てる
- 様々な業務に対応できるように訓練する
- 働きやすい環境を整える
- 担当業務を限定して求人募集をする
客観的に評価できるシステムを作る
効果的な人員配置のためには、客観的な評価システムが必要です。わかりやすい評価があると、スタッフのモチベーションを高められます。日々の取り組みによって、向いているかどうかが、わかりやすくなります。
さらに、年次評価や360度フィードバックなど、多角的な評価方法も取り入れてみましょう。歯科助手の能力と適性を正確に把握し、最適な業務に配置できます。
スキルと経験を活かせる業務に配置する
スキルと経験を考慮した配置も大切です。歯科助手の仕事への満足度と、業務の効率を高めます。本人が得意とする業務に就かせることで、仕事の質が向上し、患者へのサービスも改善されます。
例えば、人と話すことが得意な助手は受付や患者対応に、細かい作業を好む助手は器具の準備や管理、といった形です。適材適所を意識して配置しましょう。
業務の需要とピークタイムを分析する
業務の需要とピークタイムの分析は、人員配置において不可欠です。「どの時間帯」の「どの業務」に「どれだけの人手が必要か」が明確になります。戦力を集中させるタイミングを見計らいましょう。
例えば、来院が集中する時間帯には受付や診療補助の人員を増やすと、スムーズな対応が可能です。待ち時間も少なくなるでしょう。
顧客満足度に繋がるのはもちろん、スタッフにとっても働きやすい環境になります。
柔軟なシフト計画を立てる
柔軟なシフト計画を立てることも大切です。スタッフのワークライフバランスを保ちながら、歯科医院の人手不足を解消できます。
シフトに柔軟性を持たせて、個々の生活状況や希望に合わせた働き方ができるようになれば、離職率の低下にも繋がります。
様々な業務に対応できるように訓練する
様々な業務に対応できる歯科助手の育成は、歯科医院の柔軟性を高めます。歯科助手が業務の幅広い知識とスキルを持っていると、突発的な人手不足や緊急時にも対応可能だからです。
研修やワークショップを通じて、多岐にわたる業務スキルを身につけさせるようにしましょう。得意な部分を伸ばすようにすると、大きな戦力になってくれます。
働きやすい環境を整える
働きやすい環境の整備は、歯科助手だけでなくスタッフ全体の定着率を高めます。モチベーションを維持でき、仕事の効率も上がるでしょう。以下の方法がオススメです。
- 休憩スペースの設置
- 気軽にコミュニケーションができる場所の設置
職場の環境を改善し、働きやすい環境を作っていきましょう。環境作りに迷った際は、スタッフにヒアリングするのもオススメです。自分では見つけられなかった部分を希望されるかもしれません。
担当業務を限定して求人募集をする
求人時に担当業務を限定して募集することで、より適した人材を見つけやすくなります。特定のスキルや経験を持つ人材を対象にすると、即戦力となり得るスタッフの獲得が可能です。
例えば、単に「歯科助手」とするよりも「歯科医院の受付業務」とすることで、事務職や接客業を経験している人がイメージしやすい求人になります。どのような業務を任せたいのかを明確にした上で、ピンポイントな人材を募集しましょう
歯科助手の「あるある」は院長次第で大きく改善する

歯科助手の「あるある」な問題は、院長の適切な管理と指導によって改善が可能です。日々の業務で直面した際は、コミュニケーションを取りながら問題を解決していきましょう。ひいてはそれが、歯科医院全体の成長に繋がります。
もし歯科助手が活躍できる場所で悩んでいるのなら、求人の時点から担当業務を決めておく方法がオススメです。歯科医院のニーズに合わせた採用ができるため、歯科助手が活躍できる場所を作れます。
採用が難しいと考える先生方は、弊社の「求人採用セミナー」を受講してみてください。歯科衛生士から応募が集まる求人の作り方を解説した内容ですが、歯科助手も考え方は同じです。優秀な歯科助手を採用するヒントを得られるでしょう。