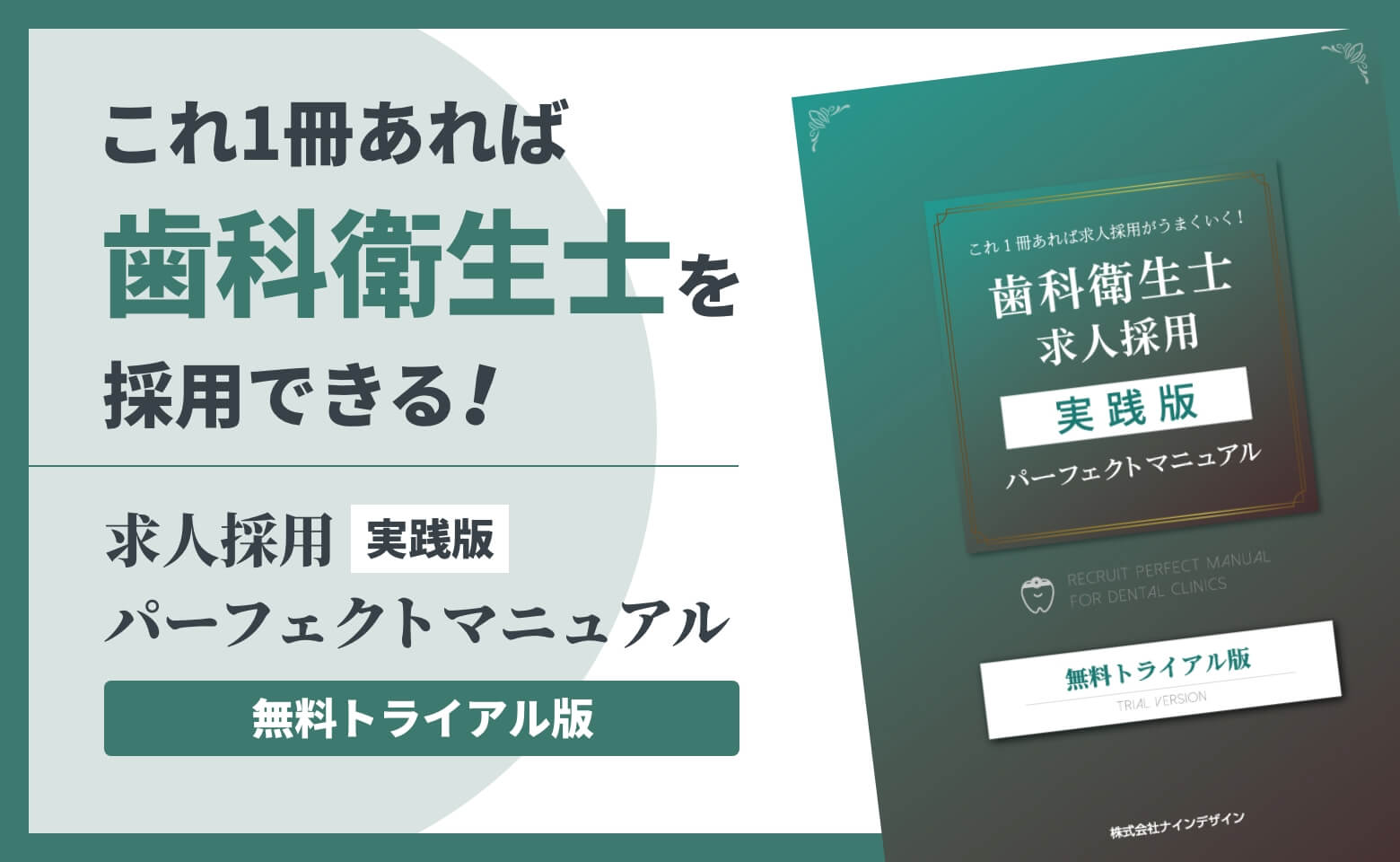また一人、優秀な歯科衛生士さんが退職を...
こんな言葉を胸に抱えている院長先生、そして現場で奮闘している歯科衛生士の皆さん。
スタッフの離職は、チーム全員の心に大きな影を落とし、残されたメンバーの疲弊にもつながってしまいます。
でも、諦めないでください。必ず状況を改善できる方法があるはずです。
今回は、歯科衛生士さんが定着しない医院によく見られる特徴と、その改善策について、現場の声に寄り添いながらご紹介していきます。
⇒「DHから応募が集まる求人の作り方セミナー」
はじめに
歯科医院を長く続けていく上で、優秀なスタッフの存在は本当に大切ですよね。
でも実際のところ、「いい人材がなかなか見つからない」「せっかく採用しても、すぐに辞めてしまう」という声をよく耳にします。
なぜこんなことが起きてしまうのでしょうか?
スタッフが定着しない歯科医院の実態

歯科衛生士の離職率はなぜ高いのか?
実は、歯科衛生士さんの離職率の高さは業界全体の課題となっています。
厚労省の調査によると、歯科衛生士さんの平均勤続年数はなんと約6年。
専門的な国家資格を持つ医療職としては、かなり短い傾向にあるんです。
この背景には、「専門性を十分に活かせていない」「将来のキャリアパスが見えづらい」といった不安や、職場環境への不満があるようです。
特に新人さんの場合、予防処置や歯科診療補助といった本来の専門業務に加えて、医療事務や受付業務まで任されることで、自身の専門性を発揮できないというストレスを感じやすいみたいですね。
スタッフが辞めやすい医院の特徴
スタッフの入れ替わりが激しい医院には、いくつかの共通点があります。
まず目立つのが、スタッフ同士や院長先生とのコミュニケーション不足。
それから、「誰が何をすればいいのか分からない」という役割分担の曖昧さで、特定のスタッフさんに仕事が集中してしまうケースも多いんです。
さらに、新人教育の体制が整っていないために、「この仕事、本当にこれでいいのかな...」という不安を抱えたまま働いているスタッフさんも少なくありません。
こういった状況が積み重なって、最終的に「もう辞めたい」という気持ちにつながってしまうわけです。
スタッフが定着しない歯科医院の共通点

1. 人間関係のトラブルが多い
職場の人間関係って、本当に大切ですよね。
でも残念ながら、多くの医院でこれが原因で退職するケースが後を絶ちません。
特によく見られるのが、次のような例です。
- スタッフ同士の連携が上手くいかず、「あの人に聞いてない」「私は知らなかった」といったトラブルが頻発
- 院長のご家族が経営陣として関わっているケースでは、立場の違いから率直な意見交換が難しく、業務改善の提案もしづらい雰囲気になりがち
- 様々な立場の方が関わる中で、誰に相談すべきかも不明確で、コミュニケーションに支障が出ている
中には「優秀だからと何でも任されすぎて疲弊してしまう」といったケースも。
こういった問題は、仕事の効率を下げるだけでなく、働いているスタッフさんのストレスをどんどん溜めてしまいます。
2. 院長・経営者のマネジメント不足
「優秀な歯科医師=優秀な経営者」とは限らないんです。
実際、多くの院長先生が診療技術は素晴らしいのに、スタッフマネジメントの面では苦手意識を持っているようです。
例えば「自費診療の推進」と「専門性の発揮」のバランスが難しかったり、スタッフからの改善提案を取り入れる機会が少なかったり。
評価基準も「なんとなく」で決まっているケースが多いんです。
これでは、歯科衛生士さんのやる気も下がってしまいますよね。
3. 給与・待遇の不満が解消されていない
歯科衛生士さんは専門職として重要な役割を担っているにもかかわらず、多くの医院では期待に見合った待遇が得られていないと感じている方が多いようです。
特に問題なのが、「キャリアやスキルがどう評価されるの?」という不透明さなんです。
例えば、「何年働いても昇給の基準が明確でない」「予防歯科のスキルを高めても給与に反映される仕組みがない」「経験年数や担当業務の違いがどう待遇に反映されるのか分からない」といった声をよく聞きます。
評価基準や昇給の仕組みが明確に示されていないことが、歯科衛生士さんの将来への不安や不満につながっているんですね。
4. 労働環境や勤務体系が過酷
「休憩時間がきちんと取れない」「急な勤務変更が多い」
...こんな状況で働き続けるのは、かなり大変ですよね。
特に歯科医院では、次のような問題がよく見られます。
- お昼時や夕方に患者さんが集中するのに、スタッフの配置が足りていない
- 「今日は忙しいから」と休憩時間を返上させられることが多い
診療の都合とはいえ、このような過酷な労働環境が続くと、心身ともに疲れ果ててしまいます。
5. 採用時のミスマッチが発生している
人手不足に困って「とにかく誰か来てほしい!」と焦って採用してしまう...。
実はこれ、すごく多いんです。
でも、歯科衛生士さんの場合、その専門性を考えると、こういった採用方法は大きな問題につながりかねません。
例えば、「予防歯科に力を入れたい」という歯科衛生士さんを採用したものの、実際には一般的な診療補助がメインで予防処置の機会が少なかった、なんてケース。
または「専門性を活かした業務に専念したい」と思って入職したのに、受付業務などに多くの時間を取られてしまうといったミスマッチも。
これでは、せっかくの国家資格を持つ専門職としての意欲も削がれてしまいますよね。
6. 教育・研修体制が整っていない
「とりあえずやってみて覚えてね」
...これって、新人の歯科衛生士さんにとってはすごく不安な言葉です。国家資格を持つ専門職として、しっかりとした技術研鑽の機会を求めているのに、それが得られないのは大きな悩みの種になっています。
特に、予防処置技術や専門的な口腔ケア、診療補助技術の向上といった、歯科衛生士として重要な専門分野について、体系的な研修制度が整っていないケースが多いんです。
これは歯科衛生士さんのキャリア形成を妨げるだけでなく、提供できる医療サービスの質にも影響してしまいます。
スタッフの定着率を上げるための改善策

1. コミュニケーションを強化し、信頼関係を築く
スタッフの定着率を上げるために、まず取り組みたいのがコミュニケーションの改善です。
具体的には次のような方法がおすすめです。
- 毎朝15分程度のミーティングで、その日の予約状況や気をつけるポイントを共有する
- 週1回は30分程度の定例ミーティングを設けて、業務改善のアイデアを出し合う。
実は、こういった短時間のミーティングには、業務連携以上の価値があるんです。
朝一番の明るい挨拶や、ちょっとした雑談を交えたコミュニケーション。
たった15分のポジティブなやり取りが、その日一日のスタッフの気持ちを明るくし、チーム全体の雰囲気を良くしていきます。
人は感情の生き物。
数字では測れない「その日の気分」や「チームの空気感」が、実は仕事のパフォーマンスや人間関係に大きく影響するんですよ。
定期的なコミュニケーションの機会を設けることで、スタッフ同士の連携がスムーズになるだけでなく、働く人たちの心も明るくなっていきます。
2. 院長・マネージャーのリーダーシップを強化する
院長先生に求められるのは、優れた診療技術だけではありません。
チームのリーダーとしてのスキルも大切なんです。
まずは、定期的な個人面談の実施で、スタッフさん一人ひとりの悩みやキャリアプランについて話し合う機会を作ることから始めてみましょう。
「この医院で長く働きたい」と思ってもらえるためには、スタッフさんの声に耳を傾けることが何より大切ですよ。
実は、「自分の考えや希望を少しでも聞いてもらえた」という経験が、スタッフさんの気持ちを大きく変えることがあるんです。
例えば「将来はこんな歯科衛生士になりたい」「こういう分野にもっと力を入れていきたい」といった想いに、院長先生が真摯に耳を傾けてくれる。
そんな機会があるだけで、「この医院で頑張ってみよう」という気持ちが芽生えるものです。
また、日々の業務の中で「あなたの頑張りをちゃんと見ていますよ」というメッセージが伝わることも、とても大切。それは必ずしも大げさな表彰や評価でなくても構いません。
ちょっとした声かけや感謝の言葉で、「この医院の一員として認められている」という繋がりを感じられることが、長く働き続けたいと思える大きな理由になるんです。
3. 給与・待遇を見直し、スタッフの満足度を向上させる
給与や待遇の改善は、歯科衛生士さんのモチベーションに直結する重要なポイントです。
臨床経験年数だけでなく、予防歯科や口腔ケアなど、各分野でのスキルレベルを評価基準に組み込んだ給与体系を整備する。
また、認定歯科衛生士などの上位資格取得に向けたサポート体制と、それに応じた待遇アップの基準を明確に示すことで、「この医院で頑張れば、自分の成長が正当に評価され、キャリアアップできる」という安心感を持ってもらうことができます。
4. ワークライフバランスを考慮した労働環境の整備
働きやすい環境づくりって、実はそんなに難しいことではないんです。
でも、その重要性は年々高まっています。
歯科医院の数が増え続ける一方で、歯科衛生士の数は減少傾向にあり、さらに少子高齢化も進んでいます。
もはや「うちの医院で働けることは特別なこと」という考え方は通用しない時代。
むしろ「歯科衛生士さんに選ばれる医院になる」という視点で、柔軟な働き方を考えていく必要があるんです。
大切なのは、歯科衛生士さんの専門性を尊重しながら、個々の生活スタイルも考慮に入れること。
今いるスタッフさんを大切にし、その人らしい働き方を支援できる医院が、これからの時代を生き残っていけるはずです。
たとえば次のような工夫ができます。
「子育て中だから時短勤務を希望したい」「認定資格の勉強と両立したい」といった歯科衛生士さんの事情に合わせて、柔軟なシフト制を導入する。
また、予防処置や歯科指導の時間を十分に確保するなど、専門性を発揮できる業務体制を整えることで、モチベーションを保ちながら長く働き続けてもらえる可能性も高まります。
実は「自分の子供の歯科検診の時間も取れない」といった声も聞かれますが、こういった状況は適切なシフト管理で十分に改善できるんです。
むしろ、そうした柔軟な対応ができる医院が、これからの採用市場で選ばれる存在になっていくのではないでしょうか。
5. 採用プロセスを改善し、適切な人材を確保する
採用時のミスマッチを防ぐために、まず大切なのは「どんな人材が必要か」をしっかり見極めること。
そのためには次のような取り組みが効果的です。
職場見学や体験実習の機会を設けて、実際の業務内容や職場の雰囲気を体験してもらう。
「こんな仕事をお願いしたい」「このくらいの経験が必要」といった条件は、最初にはっきり伝えることが大切です。
6. 研修・教育制度を充実させ、成長機会を提供する
「この医院で働くことで、歯科衛生士としてもっと成長できる!」と感じてもらえることは、定着率アップの重要なポイントです。
最新の予防処置技術や専門的な口腔ケア方法の研修機会を定期的に設ける。また、学会や外部セミナーへの参加支援、認定歯科衛生士の資格取得サポートなど、スキルアップの機会を積極的に提供することで、プロフェッショナルとしての成長をバックアップしていきましょう。

まとめ
歯科衛生士さんの定着率を上げることは、確かに簡単なことではありません。
時には、どんなに努力しても報われないように感じる日もあるかもしれません。
でも、この記事でご紹介した改善策を、たとえ小さなことからでも、一つずつ実践していくことで、必ず変化は生まれます。
なぜなら、スタッフ一人ひとりの「もっと良い医院にしたい」という思いは、必ず実を結ぶからです。
特に大切なのは、専門職としての歯科衛生士さんの情熱と能力を最大限に活かせる環境づくり。
院長先生と歯科衛生士さんが互いを理解し、尊重し合いながら、より良い職場づくりに取り組んでいく。
その一歩一歩の積み重ねが、きっと皆さんの医院を、スタッフも患者さんも笑顔になれる、素晴らしい場所へと変えていってくれるはずです。
さあ、明日から、できることから始めてみませんか?
きっと、その小さな一歩が、大きな変化の始まりとなるはずですよ。